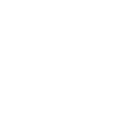1979年に公開された『エイリアン』に始まり、そのあとに長きに渡って続いてきた「エイリアン」シリーズ。その前日譚的の物語として、エイリアンの生みの親であるリドリー・スコットが監督として同シリーズに復帰した映画『プロメテウス』が2012年に公開されました。この映画の結末は明らかに続編を匂わせるものであり、5年経ってその続編がようやく公開されました。それが本作『エイリアン: コヴェナント』です。久々の「エイリアン」の名前が入った新作は、前作およびオリジナルとどのような結びつきを持つのかを執筆しました。

芸術と神話へのオマージュを多分に含んだ一作
前作のプロメテウスもそうでしたが、本作『エイリアン: コヴェナント』も、なかなかに難解な作品だと感じました。スコットの監督作品ではよく感じることですが、初見で解説なしで作品を理解することが非常に難解な一作となっていると思います。特に西洋の芸術文化や神話、宗教、哲学などの深い知識がないと理解することが難しい場面が複数あり、味わうのが難しい印象でした。
冒頭からアンドロイドが自らをデイヴィッド(ダビデの英語名)と名付けたり、『オジマンディアス』の言及があったり、『ラインの黄金』「ヴァルハラ城への神々の入城」が登場したりと西洋芸術への造詣の深さを問いかけられます。この時点で脱落してしまう人も一定数いるのではないでしょうか。テーマの明示としては有効ですが、風呂敷を広げ過ぎているようにも感じました。
そして本編に入ると目立つのが、明らかに絵画を意識した画面作りです。レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』のような分かりやすいものから、ジョン・ミルトンの『失楽園』、ダンテ・アリギエーリの『神曲』の挿絵などといった細かいものの構図を模した場面が本編を通して複数挿入されています。これらからは、監督の強いこだわりを感じました。前作の『プロメテウス』と比較すると、画面が全体的に暗いのでこれらの絵画的画面は少しわかりづらいのですが、「エイリアン」の名を冠した一作であることや、元の挿絵がモノクロなことを考えると自然だとも感じました。
マイケル・ファスベンダーの怪演が再び
映画『エイリアン: コヴェナント』でひときわ観客を惹きつけるのは、やはりアンドロイドを一人二役で演じ切ったマイケル・ファスベンダーの演技力でした。前作『プロメテウス』でも突出した演技力でデイヴィッドというアンドロイドを演じ切っていたファスベンダーでしたが、本作ではそれを上回る演技を見せていたと思います。

前作で特に印象的だったのが、見た目は生身の人間であるにもかかわらず、どうにも無機質なアンドロイドの表現でした。それを維持しつつも、本作ではさらにデイヴィッドとウォルターという2体のアンドロイドをきっちりと演じ分けました。冷静かつ無敵で無機質なアンドロイドを演じつつ、片方はそれゆえの狂気で表現し、もう片方にほんの少しの温かみを与えていたように感じました。その匙加減の塩梅が絶妙で、作品の中で群を抜いた存在感を放っていたと思いました。前作とは異なり、本作では主演としてクレジットされており、作品をまさにけん引する存在でした。
人類の滅亡
映画『エイリアン: コヴェナント』のタイトルにある「コヴェナント(Covenant)」は「契約」もしくは「約束の地」を意味します。そして本作の舞台は希望を全くないエンディングだったと思います。
前作からの物語のつながりで非常に分かりやすいのが、このシリーズでは一貫して「フランケンシュタイン・コンプレックス」がテーマとして扱われている点です。本作の冒頭では、1818年のソネット『オジマンディアス』が言及されています。後にウォルターが訂正した通り、これはパーシー・ビッシュ・シェリーの作品なのですが、デイヴィッドはこれをジョージ・ゴードン・バイロンの作品だと述べています。シェリーとバイロンは同時代の詩人で非常に親密だったことで知られていますが、中でも有名なのが「ディオダティ荘の怪奇談義」という集まりです。この集いに参加し、それをきっかけにメアリ・シェリーが書き上げた小説が『フランケンシュタイン』で、1818年に出版されました。小説の副題は「あるいは現代のプロメテウス」で、前作のタイトルおよびこの前日譚シリーズの主題へとつながります。
さらに『オジマンディアス』はエジプト王ラムセス2世の没落についてのソネットだとも考えられていますし、同じ場面で言及された『ラインの黄金』「ヴァルハラ城への神々の入城」は、神々の没落の始まりを描いています。「ヴァルハラ」は神々にとって約束の地のような意味もあらわすため、「コヴェナント」とも重なります。これだけで、約束の地に向かう希望と滅亡に向かう絶望という二つのテーマが明確に分かるようになっています。
タイトルと冒頭のシーンだけでこれらを明示するのは、やはり少し難解でした。筆者は複数のレビューを調べているうちにこういった画面の奥にある考えが見えてきました。
エイリアンシリーズとしての「プロメテウス」と「コヴェナント」
筆者はエイリアンシリーズというと閉ざされた空間で圧倒的な力をもつゼノモーフが襲い掛かかり、そんなゼノモーフからいかに逃げまどうシーンにハラハラドキドキの展開を期待していました。そして本作のPVでゼノモーフが登場し期待していまおりました。確かにゼノモーフが襲い掛かるのですが、ホラーのような緊張感はなかったです。
「エイリアン」の名を冠した正当な続編である映画『エイリアン: コヴェナント』。さまざまな言及や複線の詰まった作品です。自分のペースでじっくりと堪能できる配信で鑑賞し、自分なりの解釈を考えてみる作品となっていると思います。