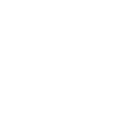禍威獣(怪獣)も原作にもいる個体をリスペクトしつつも現代作品とにも上手く溶けこんだデザインとなっており、異形でありつつも違和感は覚えない存在として君臨していた。
ストーリーも最初から最後まで中だるみすることもなく、きちんとウルトラマンが地球を守る骨太な作品となっている。最後に、EDとして流れる米津玄師「M八七」を是非歌詞を見ながら聞いてほしい。間違いなく映画の最後を締めくくるのにふさわしい楽曲となっている。
ファン待望の庵野氏による空想特撮映画
「新世紀エヴァンゲリオン」シリーズの庵野秀明氏が描く、シン・ゴジラを皮切りに日本の有名特撮作品の映像化における「空想特撮映画」の2作品目にあたる。
ウルトラマンは庵野氏自身の原点であることも大きく、制作が決定した際には大きな話題となった。(ただし、シン・ゴジラとは違い、本作で庵野氏は企画・脚本という立場である)
彼のウルトラマンにかける情熱っぷりは、大学の同級生である島本和彦氏「アオイホノオ」やパートナーの安野モヨコ氏「監督不行届」といった漫画でも良く語られている。
シン・ゴジラではゴジラを取り巻く日本の「会議」を中心に作られた映画だったが、このシン・ウルトラマンは「ウルトラマン」と人間たちが怪獣(本作では禍威獣)から日本、および地球を守ろうとする物語である。
(以後、同じ制作者の作品であるため、2作品を比較に使うことをご了承願いたい)
筆者自身は原典となるTVシリーズのウルトラマンは未視聴であり、幼少期にティガ、ダイナを見た「ウルトラマンは異星人である」「ウルトラマンが地球で活動するには人間と一体化しなければならない」と言うレベルの知識でしかなかったが、先に結論だけ述べるとウルトラマンに関する知識はそこまでなくても十分楽しめる作品だった。

ファンタジーな存在が同居する世界観のリアルさ
ウルトラマンや宇宙人、禍威獣という想像の生物が現代日本に限りなく近い世界にいる中で、映像技術が進んだこの令和で求められるのは「リアルさ」の中に自然と「ファンタジー」を混在させるか、という点ではないだろうか。
その点、ウルトラマンは非常にギリギリのラインを攻めていると感じる。
ウルトラマンが飛来して着陸した際の被害、ウルトラマンが変身した時の地表、禍威獣被害と言った点はシンゴジラでも「リアル」を感じていたが、ウルトラマンでは外星人(宇宙人)の存在が大きい。
どちらかと言えばファンタジーに大きく天秤が傾くシーンが多いが、それでもギリギリのリアルさを感じるのは、地球を狙う外星人たちが政治家たちにコンタクトを取って、条約を結んだり交渉事を行う点(つまり人間と同等、それ以上の知性がある点)である。
これがただやってくる脅威を払うだけではシンゴジラと一緒だなと感じていただろう。
また、ウルトラマンの象徴とも言える活動限界時間を伝えるカラータイマ-の存在はなく、彼の体表の色味が変わることで表現されている。
往年のファンにとって、このタイマーがないことは残念に思うかもしれないが、緊迫したシーンでタイマー音が鳴り響くのは鑑賞中の気持ちが削がれるのではと思っていたので、これは正直ありがたい変更だと感じた。

魅力的な出演者たち
ウルトラマンとなった男・神永新二を演じるのは斎藤工氏、ウルトラマンとなった経緯からかほとんど表情が無い点、
また、長澤まさみ氏演じる浅見弘子も、シン・ゴジラで言う石原さとみ氏のポジションではあるが、クレバーな面より熱血で作品の性質上もあってエネルギッシュに動き活躍している。
西島秀俊らが演じる他の禍特対メンバーはどちらかと言えば視聴者側の存在ではあるが、禍威獣対策を行う第一線で戦うメンバーであるため、随所における専門的な(と思われる)知識を披露することでその存在感はしっかりと印象に残っている。
また、外星人を演じるのは声優・津田健次郎氏や俳優・山本耕史氏が名を連ねている。彼ら二人が採用されたのは非常に興味深く、昨今のサブカルチャー人気を考えると筆者のような、ウルトラマン初心者でも興味を持ちやすいポイントとなっているだろう。
(山本耕史氏が演じる外星人のとあるセリフは、公開後一時期ネットミームとして大喜利化していたくらいだった)