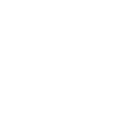1975年に公開され、日本映画史にその名を刻んだ高倉健主演の伝説のパニック映画『新幹線大爆破(1975)』。そんな有名なタイトルがNetflixと樋口真嗣監督、そして主演・草彅剛という布陣で2025年の令和に蘇りました。
本作は最新鋭の新幹線に爆弾が仕掛けられ、速度を落とせないという極限状況の中、必死に解決の糸口を探す人々の姿を描く、ノンストップ・サスペンスです。
観終わってまず感じたのは、「あ、これは樋口監督の作品だ!」ということです。新幹線に限らず管制室などが細部にまでこだわった描写は健在でした。特に東北新幹線のリアルな表現には舌を巻きました!「はやぶさ60号」がCGのみならず特撮で再現されているあたり、監督のこだわりを感じます。これはJR東日本の全面協力があってこそだと思います。
物語は、新幹線内部での爆破シーンと、裏でそれを食い止めようとする制御室の担当官や政府関係者との緊迫したやり取りが並行して描かれています。一般人のほかにも、政府の議員や今どきのYouTuberといったキャラクターが登場するあたりは、令和版ならではの味付けですね。現代的な要素が加わることで、作品に色々な深みが出ていると感じました。
ただ個人的にはもう少し踏み込んでほしかった点もいくつかありました。まず登場人物のキャラクター造形がもう少し掘り下げられていたら、さらに感情移入できたかなと。一部のキャラクターの行動には「本当に必要だったのかな?」と感じる部分もあり、そのあたりは少し惜しかったです。
そして、一番気になったのは、犯人の動機。1975年版は当時としてはかなり先進的な視点で描かれていましたが、今回の2025年版では正直、よく分かりませんでした。「もしかしたら、今の世相を反映して、動機が不明確な犯罪をアレンジしているのかな?」とも思いましたが、もう少し具体的な描写があれば、より作品に引き込まれたんじゃないかと思います。
全体的には、昔の作品が現代にどう再構築されるのか、とても興味深く観ることができました。昔のファンも、新しいファンも楽しめる部分がたくさんあるはずです!
なぜ今『新幹線大爆破』なのか? – 伝説の継承と現代的リアル
なぜ伝説的な「新幹線大爆破」を現代に蘇らせたのか。オリジナル版は、その後のハリウッド映画『スピード』にも影響を与えたほどの傑作となっています。それをリメイクすることは、とてつもない挑戦だったはずです。
「新幹線大爆破」と同じく止まったら爆破されるバスが止まったら爆破するノンストップ映画「スピード(1994)」はこちらVODから鑑賞できます。

そしてその大役を担ったのが、『シン・ゴジラ』で日本中を震撼させた樋口真嗣監督でした。オリジナル版がCGのない時代に、本物の車両やセットを使った生身の迫力で「リアルさ」を追求したのに対し、樋口監督は異なる切り口で現代の「リアルさ」に挑んでいるように感じます。それは有事の際に人々や組織がどう動き、どんな壁にぶつかり徹底的に考え抜いて映像に落とし込むという手法です。その一つひとつの手順や経緯を克明(こくめい)に描き出す様は、まさに『シン・ゴジラ』で私たちが目撃した光景の再来でした。
『シン・ゴジラ』の系譜を継ぐ、社会派パニック・スリラー
この映画が単なるパニック・スリラーではなく、現代社会の歪みを鋭くえぐり出す「社会派」としての側面を持っている点です。
『シン・ゴジラ』を彷彿とさせる多層的な展開
本作は現場と裏で動く管制官と政府関係者の動きを並行して描く多層的な展開があります。この展開は樋口監督が手掛けた『シン・ゴジラ』を彷彿とさせるところです。新幹線内部での緊迫した爆破阻止の動きと、それを食い止めようとする制御室の担当官、そして水面下で事態の収拾を図る政府関係者とのやり取りが、見事にリンクして描かれています。
爆破予告を受けた新幹線運行の管制室の担当官たちが緊迫した状況下で迅速な判断を迫られます。刻一刻と迫るタイムリミットの中で彼らがモニターに映し出される列車の位置や速度、そして現場からの情報を元に、冷静かつ正確に指示を出す様子は、彼らの張り詰めた表情から些細なミスも許されない状況での連携プレイには、思わず手に汗握りました。
また走行中の新幹線には「政府の議員」と「今どきのYouTuber」という対照的なキャラクターが乗車しています。この二人は現代における「情報」と「権力」の複雑な関係性を描き出していました。
- 情報統制と情報の自由な流通の衝突: 政府が情報を管理しようとする一方で、YouTuberのような個人が自由に情報を発信することで、予期せぬ事態やパニックが引き起こされる可能性が描かれるかもしれません。
- 真実とフェイクニュース: 公式発表と、SNSを通じて拡散される「現場の情報」の間で、何が真実なのかを見極める難しさ、あるいはフェイクニュースが混乱を招く様子が描かれることもありえます。
一つの危機に対して、政府のような巨大な組織から、YouTuberのような個人まで、様々な立場の人々がそれぞれの思惑や行動原理で反応する様子を描くことで、現代社会の複雑で多層的な側面を浮き彫りにしていると言えるでしょう。
さだまらない犯人像
オリジナル版である1975年の犯人には、社会に虐げられたことによる同情できる動機がありましたが、本作の犯人は多くを語りません。その動機や背景は意図的に曖昧なままです。
これは現代における「悪意」の質が変わったことを示しているのではないか推察します。理解も共感もできず、ある日突然、SNSでの誹謗中傷のように唐突に日常を壊しにくる不条理な存在。草彅さんは、その得体の知れない恐ろしさを、静かな佇まいと目の光だけで見事に表現していて、思わず息を呑みました。
この映画が本当に問うているのは、犯人という個人以上に、「理由の分からない脅威にどう向き合うか」ということなのかもしれません。観る者をハラハラドキドキさせるだけでなく、現代社会の脆さ(もろさ)や、すぐ隣にあるかもしれない悪意について考えさせられる、非常に深みのある一作だったと思います。
物語の世界に引き込む、美術デザインの魅力
本作の魅力はなんといっても圧倒的な美術デザインです。この映画の持つ凄まじい没入感は、ストーリーやVFXだけでなく、細部にまでこだわり抜かれた美術デザインによって生み出されています。

特に鉄道会社の総合指令室や政府の対策本部のセットは、まるで本物のドキュメンタリー映像を見ているかのような現実味で、観る者を物語の世界へと一気に引き込みます。壁一面の巨大モニターに映し出される膨大なデータ、鳴り止まない電話、飛び交う怒号。情報が溢れかえる空間は、「今、まさに日本の中枢で未曾有の危機が起きている」という途方もないプレッシャーを、観る者に我が事のように感じさせました。

また最新鋭の新幹線の運転席も同様に、完璧に再現されていました。ずらりと並んだ計器類やスイッチの一つひとつが、運転士の専門的な操作に説得力をもたらし、観る者はまるで隣に座っているかのような臨場感を味わえます。この徹底した「本物」へのこだわりこそが、荒唐無稽なはずの物語に確かな手触りと現実味を与え、私たちをすっかり物語の当事者にしてしまうのです。
そして最大級のリスペクトを込めてリブートに挑んだ樋口監督の真骨頂でしょう。特撮を用いた撮影シーンは現場では1/6スケールのミニチュア新幹線を作成し、最新技術とアナログを融合させた大迫力の映像を生み出しています。CGが発達した2000年以降で特撮というと、「昔ながらの映像技法」「今ではCGで置き換えられた技術」と思われがちです。しかし実際には、人間の五感に響く演出手段として、特撮にはいまだに大きな価値があることをあらためて実感します。
これはミッション・インポッシブルシリーズでトムクルーズとスタッフがスタントにこだわり、リアルさを求めているのに近いかもしれませんね。
まとめ:『シン・ゴジラ』の再来か? アクションと社会派ドラマの融合
樋口真嗣監督による『新幹線大爆破』は、1975年の傑作を現代に蘇らせた、単なるリメイクに留まらない一作でした。その最大の特徴は、『シン・ゴジラ』を彷彿とさせる徹底したリアリズムにあり、危機に直面した日本の組織がどう動くのかを克明に描き出す手腕は、観る者に圧倒的な没入感と緊張感を与えます。さらにその緻密な美術デザインも、本作のリアリティを確固たるものにしている大きな魅力でした。
犯人の動機が意図的に曖昧にされている点など、観る人によって評価が分かれる部分もあるかもしれません。しかし、ハラハラドキドキのエンターテイメント性と、現代社会への鋭い問いかけを両立させた本作は、間違いなく邦画の新たな地平を切り拓く傑作だと感じました。