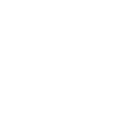モータースポーツの最高峰であるF1。このモータースポーツを題材にした映画『F1』(2025年公開)が、ジョセフ・コシンスキー(Joseph Kosinski)監督より公開されました。彼は『TOP GUN:マーヴェリック』(2022年)で知られ、今回もリアリティとビジュアルにこだわった演出だと思います。『F1』(2025年公開)もF1のモータースポーツとしてのリアリティが追求されており、アクションとリアルな映像美を融合する作風で知られ、今回も実際のF1グランプリの舞台や車両を撮影し、その臨場感を最高にリアルなレーシング映画として追求しました 。
F1とは何か? 基本から解説!
まずは本作を鑑賞する上で「F1とは何か?」という基本的な部分をまとめてみました。
F1の「F」は「フォーミュラカー」の「F」を指します。フォーミュラカーとは、車輪とドライバーがむき出しになっていて、スピードを出すことに特化したレースカーのことです。
映画冒頭で主人公のソニーが走っていたのはF1ではなく、「デイトナ24時間レース」でしたね。デイトナ24時間レースは「世界三大耐久レース」の一つに数えられるほど大規模なレースで、ロレックスがスポンサーを務めるほどの権威ある大会です。
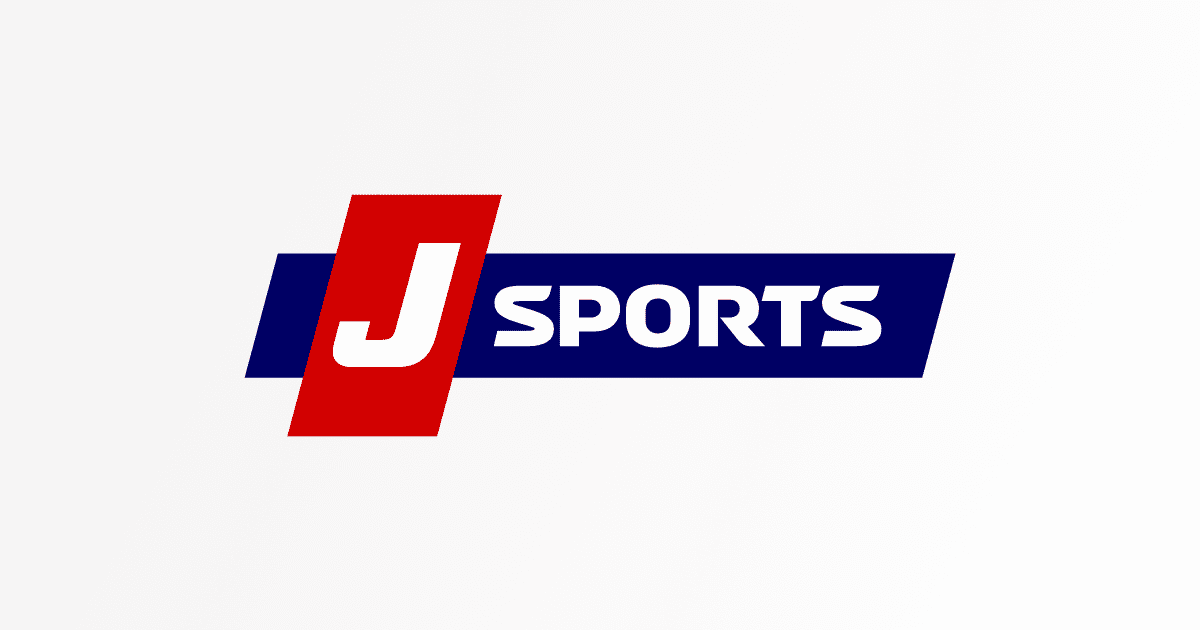
デイトナ24時間レース | モータースポーツ | スポーツテレビ局J SPORTS(ジェイ・スポーツ)の公式サイト。
F1の歴史は古く、第1回F1世界選手権が1950年にイギリス・シルバーストンで開催されました。現在F1レースは、国際自動車連盟FIAという組織が管理しています。
年間20~24戦が行われ、毎週週末、金曜と土曜に予選、日曜に本戦というスケジュールが組まれています。1位のチームには25ポイント、10位で1ポイント、それ以下はポイントなしという形で、年間を通してポイントを競い合います。1年間が52週なので、なんと年間の半分はどこかでF1レースが行われている計算になりますね。
1チームからは2人のレーサーが出場します。映画の中で、周回遅れのソニーがあえて先頭車両をブロックし、ジョシュアが追いつくアシストをするシーンがありました。これは観ていると「ずるいのでは?」と感じましたが、これも戦略的に戦うこともF1の競技性の一部なのだと思います。
またF1は総合力が試される競技であり、ドライバーに贈られる「ドライバーズチャンピオン」と、チームに贈られる「コンストラクターチャンピオン」という賞があるのもそのためです。
勝敗の鍵を握る「タイヤ」の戦略!
F1マシンは超高速でコーナーを通過するため、タイヤの摩擦力、つまり「グリップ」が非常に重要になります。現代ではマシンの高速化が進んだことで、タイヤ性能がもたらす比重が重くなっています。
F1では3種類のコンパウンド(ゴムの種類)を駆使して走行します。それぞれハード(白)、ミディアム(黄)、ソフト(赤)の3種類があり、どのタイヤを使うかはチームが決めます。劇中で登場したのはハードとソフト、そしてレインタイヤでした。
- ソフトタイヤ(赤): 柔らかいため地面に密着しやすく、グリップ力は高いですが、消耗が早く耐久性が低いのが特徴です。「早いけど脆い」タイヤと言えます。
- ハードタイヤ(白): 硬いためグリップ力は低めですが、耐久性が高く、長時間走り続けることができます。
- レインタイヤ:水はけ性能が高いタイヤ
また映画でも描かれていたように、タイヤの「温度」が高いほど摩擦が生まれ、グリップ力が高まるため、スピンせずにスピードを出すことができます。そのため、路面とタイヤの温度が上がってくるレース中盤以降に、どのタイミングでスピードを出すかがポイントになります。スタートする前にマシンがジグザク走行するのはこのグリップ力を高めるためにタイヤを温めているからですね。他にもソニーがわざとスタートを遅らせてタイヤを温めるレースもありました。
レース中には、1回以上のタイヤ交換が義務付けられており、同じタイプのタイヤを使い続けることはできません。2種類以上のコンパウンドタイヤを使用しなければならないため、映画の中でもハードとソフト、どちらでいくかなど、戦略が練られていましたね。
金曜と土曜の練習走行で、どのタイヤを使うかを決めて予選に挑み、本戦での配分を決めていくのです. タイヤ交換はまさに「策略ゲーム」であり、どこでどう使うかが勝利の鍵を握るのです。
F1マシンのその驚異のスペック!
F1は映画にもあった通り、マシンやエンジンから開発できる「総力戦」の場です。F1マシンのトップスピードは約370kmを超え、なんと1000馬力もの出力を誇ります。私たち一般人が高速道路でのスピードが100kmなので、F1はその3.5倍以上のスピードで彼らは走っているわけです.。まさに「モンスターモータースポーツの最高峰」であり、地球上で世界最速の競技と言っても過言ではありません。
🏎 モータースポーツの種類と最高速度一覧(2025年時点)
他にもさまざまなモータースポーツがありますが、オンロードでのモータースポーツをピックアップしてみました。
| モータースポーツ種別 | 最高速度(概算) |
|---|---|
| F1(フォーミュラ1) | 約360~370km/h(DRS使用時) |
| インディカー(IndyCar) | 約380km/h(オーバル) |
| WEC(世界耐久選手権) | 約330km/h(ル・マンのストレート) |
| NASCAR | 約320km/h(デイトナなどのオーバル) |
| ドラッグレース(Top Fuel) | 約530km/h(時速到達まで4秒以下) |
| スーパーGT(日本) | 約300km/h(富士スピードウェイなど) |
このとてつもないスピードで走るため、ドライバーには最大約6Gもの重力がかかります。重力の6倍もの力がかかりながら運転しているというのは、想像を絶する肉体と精神力が求められる競技なのです。
ハイテク満載のギミック
映画内で登場した気になるポイントとして、「DRS」というギミックがありました。これは「Drag Reduction System(ドラッグ・リダクション・システム)」の略で、直線で空気抵抗を減らし、一時的にスピードを上げて追い抜きをしやすくするための装置です。
F1マシンのリアウィングの上の板は通常、斜めに閉じており、車体の下に空気がかかることで「ダウンフォース」という力が生まれます。しかし、DRSを起動させると、リアウイングの上部フラップが開きます(平らに近い角度になる)。 これにより空気抵抗が減り、ダウンフォースが弱まってスピードが上がるという仕組みです。
ただし、DRSはいつでも使えるわけではありません. FIAが定めるルールの中で使用が許可されており、レース開始直後や雨の時は使用禁止です. また、「DRSゾーン」という直線区間に限定され、さらに前のマシンとの距離が1秒以内の時のみ使えるというまさに追い抜きの切り札なのです。
レースを彩る戦略的要素:セーフティカーとレッドフラッグ
映画でも度々登場するのが「セーフティカー」です。これは車の破片が散乱した時やクラッシュした車両の撤去時、作業員の安全確保、天候悪化など、コース上の安全を確保するために出動する車両です. セーフティカーが先頭を走り、全車が追い越しを禁止され、隊列で走行します. この間もレースは中断せず、周回数はカウントされ続けます。この時に全車が速度を落とすため、このタイミングはピット作業を行うチャンスとなります。
そして「レッドフラッグ」もレースの重要な要素として登場します。 これは重大なクラッシュやマシンの炎上、コースバリアの破壊など、危険な状況が発生した際に、即座にレースを中断させるものです.。全車が一旦ピットラインに戻って待機します。
面白いのは、この中断中にタイヤ交換やウィング交換、サスペンションの修復が可能になることです。重大な交換はNGですが、中断時に何をしてレースを再開するかの戦略で、その後の結果が大きく変わってきます。
レッドフラッグによる再スタート、逆転劇を生み出します。実際に2023年のオーストラリアグランプリでは、9周目でレッドフラッグが振られ、ピットでタイヤを新品に交換したフェルスタッペンが、12周目で1位を奪還しました。まさにレッドフラッグはファンにとっては、何が起きるかドキドキハラハラするドラマチックな場面でもあります。
F1は安全性を最優先としているため、アクシデントによってタイム差が縮まっても、それは競技のドラマ性として受け入れられているのです。
まさにF1は戦略戦、チーム戦でもあり「この世で一番早い者を決める」競技なのです。
F1が全面協力体制し、裏側も撮りリアリティを支える!
本作はF1が全面協力して制作されています。実際のF1が行われる週末のイベントとして撮影が行われているため、表彰台のシーンやレース中に映る観客はCGではなく、本当にレースを見に来た人たちなのです.。映画班専用のガレージも用意されていたそうです。
F1の圧倒的な臨場感を引き出すカメラワークと音響
ドライバー視点や車体に取り付けられたカメラからの映像は、まるでYouTubeの車載動画を見ているかのような臨場感が感じられます!
本作はよりエンタメに特化したダイナミックなが特徴的でした。これらのシーンはF1マシンのスピードやGを間近に感じるような映像は、本当に圧巻です!
本作も「トップガン マーヴェリック」の制作チームが手掛けており「トップガン マーヴェリック」で培われた戦闘機に搭載するカメラ技術をさらに進化させ、F1レースマシンに搭載するために、より小型・軽量化したカメラを採用したAppleのシステムが導入されたことで、それが実現できたそうです。これらシーンはドライバーを正面からのショットと対面するレースカーが間近に迫るシーンが切り替わりドライーバーの臨場感が観ていても伝わってきました。
音響もF1マシンのエンジン音がダイレクトに響き渡り、その音圧に圧倒されます。これは映画館という音響設備を通して、まさにエンジンが音という空気の振動まで伝わってきました。この音響効果が、映画のエンターテイメント性をさらに高めていると感じましたね。
諦めない夢とチームの再生が描かれる人間ドラマ
映画「F1」は、かつてF1の夢を一度は諦めた男であるソニーが、再びその舞台に戻り、本当に大切なものを見つけようとする姿を描いています。主人公のソニーがF1に復帰する動機、そして彼が直面するチームの状況と相棒となるジョシュアとの対立と信頼。それらを通して展開される人間ドラマが本作の大きな魅力です。
再生を必要とするチームとベテランの挑戦
ソニーが復帰したF1チームは、内部に問題を抱えていました。チーム売却の噂が囁かれ、若手レーサーであるジョシュアは自己中心的な走りに走り、自己保身に走りがちでした。他にも優れた女性メカニックがいたものの、彼女が作り上げたマシンは、レースを勝ち抜くためのものではありませんでした。ピットクルーも自信を失っています。そんなチームはリスクを避ける選択ばかりをして表面上はまとまっているように見えても、それぞれの方向性がバラバラで、意思統一ができていないチームであったのです。

そんなチームを目の当たりにしたソニーは、自ら行動を起こし、チームの改革を進めていきます。彼はチームを牽引する一方で、また自身もまた変化を遂げていきます。昔ながらの練習方法に固執するだけでなく、シミュレーションを取り入れるなど、一見すると頑固なソニーが現代のF1に順応していく柔軟さも見せます。
若手のF1ドライバー、ジョシュアの過酷な道のり
歳をとり頑固でソニー対して若手のドライバーとしてジョシュアが登場します。ジョシュアはチーム売却が囁かれF1ドライバーに残り続けるために、本来やりたくないSNS向けのポーズを取らざるを得ないシーンがありました。これは彼が世界的な大スターとなり、F1の世界で生き残るために必要な犠牲だったのです。

それはF1ドライバーの道のりは非常に過酷であり、ドライバー自身が数億円もの費用を負担して昇格していくケースも珍しくありません。そのため、F1チームの育成プログラムや出資者の存在、さらには親や家庭環境といった周辺環境が極めて重要になります。幼い頃からF1レーサーになるために親が全面的にバックアップしたり、元々レーサーの家系であったりと、並々ならぬ努力と支援の末にF1にたどり着くのです。
世代を超えた学びと共感
この映画は、ベテランであるソニーが若手や同僚にアドバイスを与え、彼らを成長させていく姿を通して、ビジネスシーンにおけるリーダーシップやチームビルディングの重要性を示唆しています。社会人や経営者にとっても、共感できる部分が多いのではないでしょうか。

しかし、本作が伝えるのは、カリスマ的な個人だけが強いのではなく、誰もが誰かの支えを必要とし、最終的には互いに不可欠な存在になっていくというメッセージです。それは初めのレースだとお互いがバラバラの主張をしチームとしてバラバラだったのが、最終レースは「勝利」のためにお互いがアイディアを出しあう姿がありました。まさにチームが一丸となっていました。
命をかけたレーサーたちの「それでも走りたい」という強い想いが描かれており、一度は諦めた夢が再び叶おうとする場面は感動的です。そして、その夢の達成がゴールではなく、その先にそれぞれの「やりたいこと」「やらなければいけないこと」がまだある、という描写も秀逸です。何度でも見返したくなるような、力強い作品と言えるでしょう。
まとめ:人生のハンドルを握るのは自分。
最初は好きで始めたりしたものが気づけば自分の立場や生きていくために、やりたくないことをやったり、求められるがままに立ち振る舞ったり、演じてしまうことがあるかもしれません。それはお金が目的になってしまったり、甘い誘惑に負けてしまったり、いつしか自分の人生が仕組みのために動かされているように感じてしまう時があるかもしれません。
でも、本当にそうでしょうか? 突き動かしてきたのは、ただただ「気持ちいい瞬間」のために行動し続けたいという純粋な想いではなかったでしょうか。
時代がどれだけ変わろうとも、この映画が私たちに届けてくれるのは、「人生のハンドルは、これからも自分自身で握り続ける」という熱い決心と、これからも人生を力強く走り続ける力強さを感じさせた映画でした。