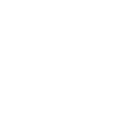アニメ映画「スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース」は、2018年にアニメ映画のトレンドを根底から変えた『スパイダーマン:スパイダーバース』の続編です。本作は、前後編構成の前編として位置づけられています。後編にあたる「スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース」は2024年に公開予定ですが2027年に延期されてしまいました。

注目すべきは、総勢250体以上ものスパイダーマンが登場するという圧倒的なスケール感だ。各次元から集結した多様なスパイダーマンたちが、それぞれ異なる絵柄とアートスタイルで描かれ、一つの画面に同居する映像は、もはや実験映画の領域に達している。
映像美と演出の革新性
水彩画とダ・ヴィンチの衝突
本作はやはりその映像的な革新でしょう。冒頭でグウェン・ステイシーのパートから始まるドラムの音に合わせて抽象絵画的な図形が踊り狂い、水彩画のような背景が彼女の心情に呼応して滲んでいく演出は圧巻シーンから始まります。特に印象的なのは、この水彩画世界にレオナルド・ダ・ヴィンチのデッサンから飛び出したようなヴィランが侵入するシーンで、異なるアートスタイルの激突は視覚的快楽の極致と言える。
各次元の独創的なアートデザイン
本作ではさまざまなスパイダーマンの世界を横断するのが特徴です。スパイダーマン・インディアの世界では、インドのチトラ・カタからインスピレーションを得た曼荼羅風のカラフルな映像が展開されます。そしてスパイダー・パンクの世界は70年代イギリスのパンクカルチャーを体現したモンタージュ・コラージュが動き出すような表現で、そのアナーキーな性格を完璧に表現している。ミゲル・オハラの未来世界ヌエバ・ヨークは、80年代ディストピアSF映画を彷彿とさせる均一化された世界観で、シド・ミードの影響を感じさせます。
このような多種多様なアート的な映像演出が本作の特徴であり、これを受け入れられるかが本作の評価が別れるところだと思います。
物語構造と親子関係の深化
ミニマムながら普遍的なテーマ
前作「スパイダーマン:スパイダーバース」で確立されたロード・ミラー・コンビの作家性は、本作でより洗練された形で発揮されています。マイルスと両親の三者面談から始まる序盤は、大学進学を巡る現実的な家族の葛藤を描き、壮大なマルチバースの設定と対照的なミニマムさを保っている。
また前作が「マイルスがスパイダーマンになる物語」だとするなら本作は、「父親がマイルスの成長を受け入れる物語」へと重心を移しているのも特徴でした。父親が瓦礫となったアルケマックス社を見つめるシーンでは、青空が反射したシートが海のように見え、息子の未来への旅立ちを前に父が一人佇む美しいビジュアルで父性の心境を表現しています。

これはマイルズだけではなくグウェンにも言えることで、「子と父親」との関係が本作の特徴でもあります。
キャラクター性とテーマの深化
グウェンの成長:孤独から仲間への物語
前作では脇役的な位置づけだったグウェン・ステイシーが、本作では事実上のもう一人の主人公として昇格していて、本作ではマイルズとのW主人公との立ち位置となっていました。それは冒頭のナレーションから始まる彼女の物語は、前作のマイルスと対比的な構造を持っています。
前作でマイルスが「何者になりたいのか」という自己探求の旅を経験したように、本作でグウェンもまた「自分が何者であるか」を父親に受け入れてもらう物語を歩んでいます。しかし、その描写は前作よりもさらに複層的です。彼女の世界の背景色がトランスプライドの3色で構成され、部屋には「Protect Trans Kids」のポスターが貼られるなど、セクシャリティのメタファーとして機能する要素が随所に散りばめられています。
物語の終盤、父親が「お前は私の最高傑作だ」と受け入れるハグシーンは、本作最高潮の感動シーンです。前作でマイルスが父親から愛を確認されたように、グウェンも父親からの無条件の愛を獲得し、一旦の成長を完了させます。さらに注目すべきは、最後に彼女が「バンド」を組むことです。前作で孤独だったグウェンが、ついに仲間を見つけたという象徴的な描写で、彼女なりの「誰でもスパイダーマンになれる」を体現しています。
マイルスの進化:受動的ヒーローから能動的革命家へ
マイルスの描写はより複雑で挑戦的になっています。前作では「スパイダーマンになること」が目標だったマイルスが、本作では「既存のスパイダーマンの物語を否定すること」へとシフトしています。これは単なる成長ではなく、パラダイムシフトと呼ぶべき変化です。
前作で父親の「どんな道を選んでくれてもいい、お前を愛している」という言葉に支えられてヒーローになったマイルスは、今度は母親の「どこに行ってもそこがあなたの居場所。胸を張って」という言葉で旅立ちます。この変化は、保護される存在から自立する存在への転換を象徴しています。
しかし最も重要なのは、スパイダー・ソサエティでの経験です。ミゲル・オハラから「マイルスは本来スパイダーマンになる運命ではなかった異常分子」だと告げられても、彼は運命を受け入れることを拒否します。「大いなる力には大いなる責任が伴う」という従来のスパイダーマンの信条に対し、「そんな責任を負わなくていい」と反発する姿勢は革命的です。
ピーター・B・パーカーの父性獲得
忘れてはならないのは、前作で人生に疲れ切っていたピーター・B・パーカーの変化です。本作では彼が父親になっており、マイルスとの関係性も師弟から父子に近いものへと発展しています。しかし同時に、スパイダー・ソサエティの一員として、マイルスを制止する側に回らざるを得ない複雑な立場も描かれます。この矛盾した感情の描写は、大人になることの複雑さを象徴しており、前作の単純なメンター関係から大きく発展しています。
現代社会への鋭い視座と作品の限界
デジタル時代の寓話としての秀逸さ
本作が優れているのは、マルチバースという設定を通じて現代社会の本質を描き出している点です。スパイダー・ソサエティは、SNS時代における我々の状況の完璧なメタファーとして機能しています。AIのライラによって管理され、アルゴリズムが検出した「アノマリー(異常分子)」を排除するシステムは、まさにSNSのエコーチェンバー現象そのものと感じます。
ミゲル・オハラが死んだ目でAIの指示に従ってマルチバースを管理する姿は、アルゴリズムに支配されて自分のタイムラインを形成する現代人への痛烈な風刺でもあります。マイルスの「俺はアルゴリズムに支配されないぞ」という叫びは、デジタルネイティブ世代の反骨精神を代弁しており、極めて現代的なメッセージ性を持っています。
情報過多がもたらす功罪
本作はアニメーションとして野心的に挑戦した作品と言えるでしょう。ただこうした野心的な試みが必ずしも成功しているとは言い難い側面もあります。それは250体を超えるスパイダーマンの登場と、それぞれが異なる絵柄で描かれる映像は、確かに視覚的インパクトは絶大ですが、同時に情報量の過多による弊害も生み出しています。
初見での鑑賞では消化しきれない要素があまりにも多く、映像に圧倒されて肝心の物語への集中が削がれる瞬間があります。これは複数回の鑑賞を前提とした構成とも言えますが、一般観客にとってはハードルの高さにつながりかねません。アート映画的な実験性と大衆映画としてのエンターテイメント性のバランスが、時として崩れる印象も否定できません。
二部作構成の戦略的判断と課題
本作最大の課題は、前後編構成による物語の未完成感です。来年公開予定の『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』への橋渡し的性格が強く、マイルスの物語は完全にクリフハンガーで終わります。確かにグウェンの物語は本作内で一応の完結を見せており、二人の主人公という構成で前編としてのバランスを保とうとする意図は理解できます。
しかし、観客が最も感情移入しているマイルスの物語が宙吊り状態で終わることによる消化不良感は避けられません。これは商業的な戦略としては理解できるものの、一つの映画作品としての完成度を考えると、やはり物足りなさが残ります。
革新と継承のバランス
それでも本作が傑作たる所以は、革新的な映像表現と伝統的な物語構造を高次元で融合させている点にあります。父と子というロード・ミラー・コンビが一貫して描いてきた普遍的テーマを軸に、現代社会への批評性を込めた作品として昇華させています。過去のスパイダーマン作品への敬意を払いながらも、それを破壊して新しい物語を創造する姿勢は、まさに本作が掲げる「あなたの物語を作りなさい」というメッセージの体現でもあります。
まとめ:革命的映像体験が魅せる新たなスパイダーマン伝説
アニメ映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』は、映像表現の革新と普遍的な物語の融合において、アニメーション映画の新たな地平を切り開いた。水彩画とダ・ヴィンチの衝突が象徴するように、異なる価値観やアートスタイルが共存する現代社会への回答を、マルチバースという形で提示している。
マイルスの「運命をぶっ潰す」宣言は、大人が決めたレールに従うことを拒否する若い世代の叫びでもある。果たして彼は、アルゴリズムと大人の責任から解放されて、真に自分だけの物語を紡ぎ出すことができるのだろうか。
来年公開の後編『ビヨンド・ザ・スパイダーバース』への期待と共に、我々は今一度問いかけたい。あなた自身の物語を、あなたは本当に自分の手で書いているだろうか、と。
執筆時点だと続編の「スパイダーマン:ビヨンド・ザ・スパイダーバース」として2027年に公開予定です。