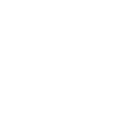映画『TAR/ター』は、MeToo運動やキャンセルカルチャーが社会現象となった2020年代だからこそ描ける、権力者の転落劇が展開されます。
ケイト・ブランシェット演じる主人公リディア・ターは、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団の女性初の主席指揮者という輝かしい地位に就いています。また彼女はレズビアンであることを公表し、パートナーの女性と養子の娘と暮らす現代的な家族を築いています。
彼女は、まさに「時代の寵児」とも呼べる存在です。しかし、冒頭で象徴的に描かれるレコード選びのシーンが物語ります。歴代の名指揮者のレコードジャケットには男性ばかりが映っており、彼女はその上に立ちながら足で選んでいくのです。この皮肉な映像が、本作の核心を端的に表現しています。
指揮者という役柄に込められた権力の象徴とブランシェットの完璧な体現
映画『TAR/ター』は、指揮者という職業設定が、本作において絶妙な効果を発揮しています。オーケストラにおいて、指揮者は文字通り時間の支配者です。演奏の開始も終了も、テンポの緩急も、すべて指揮者の意思で決定されます。これは現実社会における権力構造の完璧なメタファーと言えるでしょう。
そして、この複雑で象徴的な役柄を演じ切ったケイト・ブランシェットの演技は、まさに圧巻というべきでしょう。ベネチア国際映画祭で主演女優賞を受賞したのも納得の、独壇場とも呼べる存在感を発揮しています。
ブランシェットが演じるターは、極度のコントロールフリークとして描かれます。それは隣家の呼び鈴の音に苛立ち、自分でその音を口ずさんだりピアノで表現しようとする姿は、彼女の支配欲の強さを物語っていますが、こうした細やかな心理描写をブランシェットは見事に表現しています。権力の頂点にいる時の自信に満ちた表情から、音大での指導シーンで生徒の貧乏ゆすりというささいなノイズにまで反応し言葉巧みにその生徒を押し込めようとする支配的な瞬間、そして徐々に追い詰められていく過程での微細な心理変化まで、すべてが説得力に満ちています。

共演のノエミ・メルランも謎めいたオルガ役で印象的な演技を見せていますが、やはり本作はブランシェットが権力者の心の奥底にある脆弱性と傲慢さを同時に表現するための映画と言っても過言ではないでしょう。指揮者という絶対的権力者の役柄と、それを完璧に体現した名女優の融合こそが、本作最大の見どころなのです。
映像美と音響の完璧主義が生む芸術的野心と観客との距離
トッド・フィールド監督の演出は、視覚的にも聴覚的にも極めて洗練されていました。それはシーンのどのカットも構図が絵画的で、特に音楽ホールでの長回しの撮影は圧巻です。
この長回しという「エゴの強い」撮影手法が、主人公のキャラクターと重ね合わされ、物語の終盤で皮肉として機能する構成は見事と言えるでしょう。音響面でも、指揮者が題材だけあって細部まで計算し尽くされ、クラシック音楽の専門用語が飛び交う会話シーンの緻密さがあります。
しかしながら、この芸術的完璧主義こそが、本作の最大の課題でもあるように感じます。それは本作が2時間半を超える長尺に対して、エンターテインメント性が明らかに不足しているのです。
筆者はクラシック音楽の専門知識がない身にとって、会話についていくこと自体が困難でした。また退屈に感じる場面も多かった印象です。音楽をテーマにした「セッション」のような同じ音楽系のサイコスリラーと比較すると、分かりやすさという点で大きく劣ります。「セッション」がドラムという楽器の迫力と師弟関係の分かりやすい対立構造で観客を引き込んだのに対し、『TAR/ター』は意図的に観客を突き放すような作りになっています。まさに芸術性を追求するあまり、娯楽性を犠牲にした典型的な作品と言えるのです。
複雑な権力構造が問いかける現代社会への挑戦状
本作の最大の特徴は、その複雑さと解釈の多様性が現代社会への鋭い問題提起として機能していることでしょう。主人公ターがレズビアンの女性でありながら、実質的には旧来の男性的価値観を体現している構造は、現代社会の権力構造の複雑さを象徴していえるでしょう。
ターは形式的には同性愛カップルでありながら、実際の関係性は伝統的な「夫と妻」の役割分担に近く、料理や育児は主にパートナーが担当している現実は、表面的な多様性の裏にある本質的な問題を浮き彫りにします。
この複雑さは、キャンセルカルチャーという現代現象を考察する上で重要な意味を持ちます。単純な善悪二元論ではなく、権力者であり同時にマイノリティでもあるという矛盾した立場の人物を通して、現代社会が直面する根深い問題が描かれているのです。マイノリティが権力を握った時、果たして世界は良い方向に変わるのか。それとも権力構造そのものが腐敗の源なのか。
終盤のアジアでのコンサートシーンも、この問題提起の延長線上にあります。初心に返っての再出発と見るか、相変わらず権力志向の表れと見るか、あるいは東南アジアを見下した描写と捉えるかは、観客それぞれの価値観に委ねられている演出に感じました。
それはいずれの解釈も現代社会における権力、差別、そして真の平等とは何かという根本的な問いへと収束していきます。トッド・フィールド監督は、明確な答えを提示するのではなく、観客自身に考えさせることで、より深い社会的議論を促しているのです。
まとめ:娯楽映画と芸術映画の狭間で問われる映画の価値
映画『TAR/ター』は、現代映画界における「娯楽映画」と「芸術映画」の対立構造を象徴する作品であり、かなり難解な作品でした。本作は同様に観客を選ぶ芸術映画として、宮崎駿監督の『君たちはどう生きるか』、テレンス・マリックの『ツリー・オブ・ライフ』、クリストファー・ノーランの『テネット』などが挙げられます。これらの作品に共通するのは、作家性を前面に押し出した結果、一般的な娯楽映画の文法から大きく逸脱していることです。その一方で、同じく芸術性を追求しながらも観客に寄り添った『ブラック・スワン』や『ファントム・スレッド』のような作品もあり、芸術性と娯楽性の両立は決して不可能ではありません。
しかし、『TAR/ター』の真の価値は、まさにこの「観客を選ぶ」姿勢にあるのかもしれません。現代社会の複雑な権力構造とキャンセルカルチャーという現象を正面から描き、簡単な答えを提示しない姿勢は、映画が単なる娯楽を超えた芸術表現であることを感じさせてくれます。
ケイト・ブランシェットの圧倒的演技と映像美だけでも一見の価値はありますが、何より現代社会を生きる私たちにとって避けて通れない問題を扱っている点で、単なる芸術映画を超えた意義を持っています。
「全ての観客に愛される必要はない」。そう割り切った上で、真に考えさせられる映画体験を求める観客には、間違いなく報われる作品でした。それは観終わった後に残る複雑な感情と、答えのない問いこそが、この映画の真の価値なのかもしれません。