舞台は第二次世界大戦中のドイツで物語は戦前から始まり、戦時、戦後移り変わっていきます。原作はオーストラリアの作家マークス・ズーサック(Markus Zusak)の世界的ベストセラー小説『The Book Thief(邦題:本泥棒)』を原作としています。2005年の発表以来、40以上の言語に翻訳され、全世界で1,600万部以上を売り上げるなど、多くの人に読み継がれている名作です。
本作は物語の語り手が「死神」であるというユニークな構成と、戦時下のドイツを舞台に「読書と言葉」の意味を見つめ直す深いテーマは、YA(ヤングアダルト)文学を超えて幅広い世代に愛されています。
静かにだが確実に心に響く、言葉と命の物語
第二次世界大戦下のドイツ、ナチスの影が色濃く広がる社会の中で、一人の少女リーゼルが本と出会い、言葉を手に入れていく姿を描いたのが映画『やさしい本泥棒』です。
この映画には銃声や戦車でのシーンなどの第二次世界大戦派手な戦闘シーンはありません。描かれるのは、爆撃の音に怯えながらも「日常」を懸命に生きようとする人々の姿です。そんな世界の中で物語の主人公であるリーゼルは読書を通して心を広げていく少女です。また他にも本を隠れて読むユダヤ人青年、ぶっきらぼうながらも温かい養父母、スポーツが得意な少年が登場し、それぞれ人物が静かに、しかし確かに劇中の時代を生きています。

そしてとくに印象的だったのは「死神」の語りです。皮肉と優しさを交えたその視点は、戦争の中で命が失われていくことの重さと儚さを、より深く伝えてきます。
本が紡ぐリーゼルの成長と人々の絆、そしてその先に
映画「やさしい本泥棒」は当初文字の読めなかったリーゼルの成長にあると思います。読み書きができなかったリーゼルは、養父ハンスの優しさによって、墓掘り人の手引書という最初の本と出会い、文字を学び始めます。この本との出会いは彼女にとって死と向き合うきっかけにもなりました。
ナチスによる焚書を目の当たりにし広場で悪影響のある本を燃やされる中、リーゼルは燃え残った「透明人間」を拾い上げ、本の知識への渇望を募らせます。そして町長婦人の書斎との出会いは、リーゼルに本の広大な世界を開きました。また、ユダヤ人マックスとの出会いは、リーゼルと本との関係をさらに深めます。マックスはリーゼルに「この本を自分の言葉で埋め尽くすように」と赤い本を贈り、リーゼルは自分の物語を綴り始めます。

そして戦争が激化し空襲の恐怖が迫る防空壕で、リーゼルが人々に物語を語り聞かせる場面は、彼女が本を通して得た言葉の力が、人々を勇気づけ、心を繋ぐ役割を果たすことを示しています。本を読むことから始まった彼女の旅は、最終的に自ら物語を紡ぎ出し、他者と分かち合うことで、困難な時代を生き抜く力と人との絆を育んでいったのです。リーゼルにとって本は、自己表現の手段であり、喪失を乗り越え、愛と希望を見出すための道標でした。
心を動かされた「家族」の姿と「死神」の語り
この映画は、第二次世界大戦中のドイツを舞台に、戦前から戦後へと時代が移り変わる中で展開されます。血のつながりがないリーゼル、老夫婦、そしてユダヤ人のハンスという4人が、まるで本当の家族のようになっていく姿が印象的でした。様々なシーンがある中で、特に私が好きなのは、最初こそ口の悪かった養母ローザが、養父ハンスの病気が治ったことをリーゼルに伝えるシーンです。彼女の不器用ながらも温かい愛情が垣間見え、深く心に残りました。
また他にもジェフリー・ラッシュ演じる養父ハンスの深い愛情や、エミリー・ワトソン演じる養母ローザの厳しさの中にある優しさも心を揺さぶられます。彼らの優しさは危険を顧みずユダヤ人青年マックスを匿う姿は、人間性の尊さを教えてくれる映画だと実感しました。これは第2次世界大戦という重い悲しい物語のはずなのに、さりげないやさしさで溢れていました。
そして、映画の中で所々に登場する語り部。最初は誰の声だろうと不思議に思っていましたが、「死神」だったのですね。原作では死神が少女リーゼルを見守る物語だと知り、その視点から語られることで、単なる悲劇ではない、より深い人間ドラマが描かれていることに納得しました。
舞台ミュージカルとしての展開
「やさしい本泥棒」は、2022年にイギリスで舞台ミュージカル『The Book Thief』としても上演されました。脚本はベストセラー作家ジョディ・ピコルトとティモシー・アレン・マクドナルド、音楽はディズニー作品などでも活躍するエリサ・サムセル&ケイト・アンダーソンのコンビが手がけています。
残念ながら映像配信はないもようですが、キャストレコーディングも配信されています。
▶︎ 公式サイトはこちら
まとめ:言葉と繋がりの尊さを教えてくれる感動作品
本作は、戦争の過酷さの中で、本と人々の温かい交流がもたらす希望を描いています。主人公リーゼルが本を通して文字を学び、世界を知り、そして人々と心を通わせていく様子は、観る者の心を揺さぶります。
第二次世界大戦下のドイツを舞台にし、戦争の悲劇を描きながらも、同時に人間の希望や優しさにも光をあててくれる、静かで、でも確かな感動が、あとからじわじわと胸に広がる…そんな映画でした。
「読むこと」は、生き抜くことだった。「言葉を知ること」は、他人とつながることだった。
そんな当たり前のことが、この映画ではとても尊く感じられます。
感動的で心温まる物語はもちろんのこと、それを支える俳優たちの名演、そして「死神」というユニークな語り部が、観る人の心に深く刻まれることでしょう。きっと、言葉の力と人との繋がりの大切さを再認識できるはずでると思います。



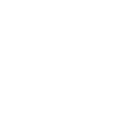

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49bdc22d.ea40f7a5.49bdc22e.a2053dba/?me_id=1425479&item_id=10229216&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fscarlet2021%2Fcabinet%2F20250524-4%2F4152088354.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)


